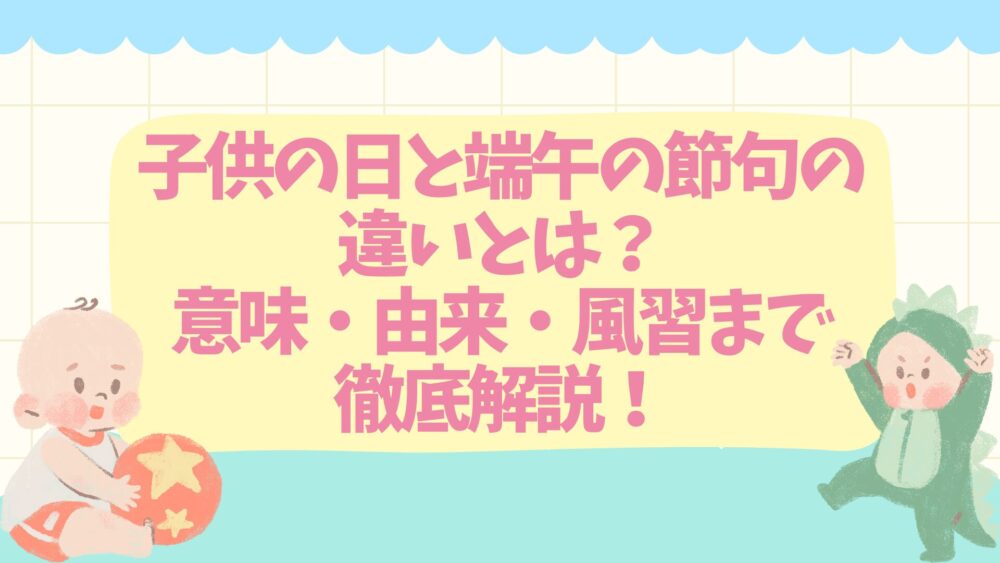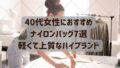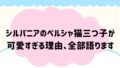端午の節句はなぜ男の子の日と言われるのか?
端午の節句はなぜ男の子の日と言われるのか?について深掘りしていきます。
それでは、なぜ男の子に特化した行事になったのかを見ていきましょう。
中国から伝わった厄払いの風習
端午の節句は、もともとは中国で「邪気を祓う日」として定められた行事でした。
古代中国では、旧暦の5月5日が「病気や災厄が起きやすい日」とされていて、人々は菖蒲や蓬を使ってその邪気を払っていました。
この風習が奈良時代に日本へ伝わり、宮中行事としても取り入れられたのが始まりです。
当初は男女関係なく、身を清める日として存在していたんですよ。
でも、日本に伝わってから徐々に「男の子の節句」へと変わっていったんです。
文化って、伝わっていく中で意味が変わるのがおもしろいですよね〜。
武家社会での男児の成長儀礼
武家社会になると、端午の節句は「男の子のための日」としての性格を強めていきました。
理由は、「菖蒲」という言葉の音が「尚武(武を重んじる)」と同じだから。
この言葉遊びのような発想から、武士の家では端午の節句を「男児が強くたくましく育つように」と願う行事にしていったんです。
鎧や兜を飾るのも、「いざという時に戦えるように」という意味が込められていました。
当時の男の子は、小さい頃から将来の戦に備えるべき存在だったんですね。
だからこそ、端午の節句は男子の健やかな成長を祝う大切な儀式になったんです。
鎧兜や鯉のぼりの意味
今でもお馴染みの「兜」や「鯉のぼり」は、端午の節句の象徴ですよね。
兜や鎧は、まさに武士の象徴であり、「身を守る」意味があります。
病気や災いから守るお守りとして飾られていたんですね。
一方、鯉のぼりは「鯉が滝を登って龍になる」という中国の故事から来ています。
逆境にも負けず、立派な人間に成長してほしいという親の願いが込められているんですよ。
今では「マンション用の小型こいのぼり」なんかも人気で、時代に合わせて形を変えてるのも面白いところです。

現代における男の子の象徴
現代においても、端午の節句は「男の子の健やかな成長を願う日」として定着しています。
ただ、今は家族の在り方も多様化していて、「女の子と一緒に祝う」家庭も増えてきていますよね。
また、伝統的な行事を通じて、日本の文化や歴史に触れさせたいという思いで祝うご家庭もあります。
保育園や幼稚園でも、「こどもの日」としてイベントを開くことが多く、端午の節句との違いが曖昧になっている側面もあります。
それでも、鯉のぼりや兜には「子どもを想う親の気持ち」がたっぷり詰まっていて、そこに込められた思いは今も昔も変わらないですね。
子供の日はなぜ5月5日?その意味とは
子供の日はなぜ5月5日?その意味とはについて解説します。
では、この日付の背景と意味を見ていきましょう!

五節句のひとつ「端午の節句」との関係
5月5日は、もともと「端午の節句」として知られる日です。
端午の節句は、江戸時代には「五節句(ごせっく)」のひとつとされ、年中行事として定着していました。
五節句の中でも端午は特に重要で、武士の家では男児の成長を祝う意味合いを持っていたんです。
その端午の節句に合わせて、1948年に「こどもの日」として法律で祝日に制定されました。
つまり、歴史的な流れの中で、もともと行われていた風習に近代的な意味づけを加えた形なんですね。
祝日が文化と重なることで、親しまれやすくなったとも言えるかもしれません。

戦後の国民の祝日として制定
「子供の日」は、日本が戦後の復興期にあった1948年に、国民の祝日として制定されました。
それまでの日本は、戦争によって大きな被害を受け、国として新しい価値観が求められていた時代です。
そんな中で、「子どもを大切にしよう」「未来を担う子どもたちの健やかな成長を願おう」という思いが込められたんですね。
端午の節句という文化的な背景に乗せる形で、現代的な意味を加えて制度化された、というのがポイントです。
これは、日本が未来に向けて歩き出す象徴的なメッセージだったとも言えますよ。

「こどもの幸せと母に感謝する日」の意味
意外と知られていないのが、「子供の日」は「母に感謝する日」でもあるということ。
祝日法では、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と明記されています。
つまり、子どもだけでなく、子どもを育てる親——特にお母さんへの感謝の気持ちも含まれているんです。
実際、家族みんなでレジャーに出かけたり、ごちそうを囲んでお祝いする家庭も多いですよね。
この日が「家族の絆を再確認する日」としても機能しているのは、とっても素敵なことだと思います。

男女問わず祝う日に変化
昔の端午の節句は、男の子中心のお祝いでしたが、「子供の日」はすべての子どもを祝う日です。
男女の区別なく、すべての子どもの健やかな成長を願う意味が込められています。
そのため、こいのぼりや兜などの飾りつけも、今では「子どもの日」のシンボルとして親しまれています。
現代では性別にとらわれず、家庭ごとの自由なスタイルでお祝いするのが主流になっています。
お祝いの形に正解はなくて、子どもたちが笑顔になれるなら、それが一番の答えなのかもしれませんね。
まとめ
子供の日と端午の節句は、同じ5月5日ですが、起源や意味、対象が異なる行事です。
どちらも子どもを思う気持ちから生まれた大切な文化であり、今では家族みんなで楽しむイベントとして広がっています。
違いを知れば知るほど、もっと深く楽しめるはず。
ぜひ今年の5月5日は、歴史に思いをはせつつ、家族で素敵な時間を過ごしてくださいね!